今月の総合安全保障プロジェクトの月次報告は、中川真紀研究員による「海峡雷霆-2025A」。中国人民解放軍が4月初めに台湾周辺海空域で実施した軍事演習の概要、注目点などを分析・評価し、わが国に対する影響も考察した。
早朝第1部は、国会議員をはじめ企画委員などに対し、昼からの第2部は、主要メディアに向けて発表した。
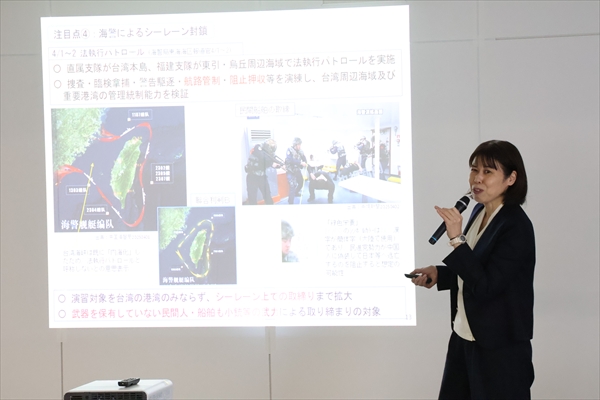
第1部:総合安全保障プロジェクト月次報告会(午前8時~9時)
中川研究員による「海峡雷霆-2025A」に関する発表概要は以下のとおり。
【概要】
最初に今回の演習に際して、主催の人民解放軍東部戦区が作成したアニメーション作品を紹介。これを見ると、演習の意図が分かりすく表現されている。台湾南部から緑色の害虫(緑は民進党のカラーで害虫は頼清徳氏)が全島を侵食しようとしているので、火を放ち(軍事力の行使)、箸で摘まんで駆除するという筋書きである。
〇演習の概要
本来、中国の演習は秋頃が訓練最盛期で重要な統合演習などは基本的に非公表である。しかし、それ以外の聯合利剣演習のように命名された演習(冠演習と呼称)は公表され、基本的に国内外に対するメッセージ性が強い。今回の演習も冠演習で、その内容は重要なメッセージと受け取る必要がある。
本演習は東部戦区主催で「海峡雷霆2025A」と統合演習で構成され、陸・海・空・ロケット軍等により台湾周辺に展開し、海空戦備警戒パトロール・総合支配権の奪取・対艦/対地攻撃・要域及びシーレーン封鎖等を演練した。
まず空軍は数十機の戦闘機と爆撃機が台湾島内の高価値軍事目標を模擬攻撃し、海軍は艦艇により多方向から台湾の港湾等を封鎖し、ロケット軍は短距離弾道ミサイルDF-15Bを発射陣地へ展開し、多目標への波状攻撃を訓練した。いずれも陸軍以外は実弾射撃未確認で、台湾本島への接近度合いを高めない意図がうかがえる。
〇注目点
・空母編隊の「海上封鎖」
海軍で参加した艦艇、軍用機の総数は、特筆するほどの数ではなかったが、南部線区隷下の「山東」空母編隊が東部戦区指揮下で「海上封鎖」要領を演練した可能性がある。今回は昨年の聯合利剣Bにはなかった「立体封鎖」という表現があり、空母艦載機を利用した封鎖の要領を重点的に検証したものと思われる。
・多連装ロケット砲のインフラ攻撃
陸軍が多連装ロケット砲(PHL191)の実弾射撃演習を実施した。場所は浙江省の南漁山射爆場で、報道画像と衛星画像を分析すると、台湾南部の永安LNG陸揚げ基地を模擬したことが伺える。しかも、模擬目標を実物の1/10の大きさに作り、精密打撃を行える能力の高さを示した。台湾のエネルギー事情は、発電の4割以上がLNGに依存しており、台湾市民に対し生活混乱を招くという脅しではないかと考えられる。
・超音速対艦弾道ミサイル
空軍爆撃機による訓練では、H-6K爆撃機にYJ-21超音速対艦弾道ミサイルの装着を初めて確認した。当該爆撃機の行動半径は3500kmで、米軍基地のあるグアムが行動可能範囲である。有事の際における米艦艇群の接近阻止を演練した模様である。
・海警によるシーレーン封鎖
海警部隊は、直属支隊が台湾本島周辺に、福建支隊が東引・鳥丘周辺海域で法執行パトロールを実施した。内容は、捜査・臨検・拿捕・警告駆逐・航路管制・阻止押収であり、海域が港湾だけでなくシーレーンへと拡大した。また、台湾海峡が演習海域から外れた図を示したが、すでに海峡は内海化したのでパトロールする必要はないとの表明であろう。
・海上民兵との連携
海上民兵船と思われる3隻の民間船が海軍艦艇と台湾花蓮港沖で演練を行った。これは「海上封鎖」を行う海軍艦艇と海警船の他に、民兵船を監視役として運用した可能性が高い。海上民兵が戦区レベルの統合演習に加わるまで軍との連携が深化していることを示している。台湾東方沖で民兵船を利用した訓練を実施したことは、日本の尖閣諸島でもグレーゾーン時に民兵を活用することが示唆される。
〇日本への影響
今回の演習は、中国軍の訓練サイクルにおいて、年度の早い段階から統合訓練を実施しており、訓練と実戦が明確でないグレーゾーン行動を常態化させ、侵攻の兆候を曖昧化させる狙いがある。演習から戦争への判断が迅速に行えなければ、対応に遅れを生じることになり、要注意である。
加えて、東部戦区の軍・海警・民兵の連携が深化していることから、尖閣諸島などへの対応に的確な対応が必要になる。
最後に、台湾への対インフラ精密打撃能力が向上していることから、日本国内重要インフラの防空能力や反撃能力の早期整備が必要となるだろう。
資料PDF 海峡雷霆2025A
第2部:総合安全保障プロジェクトメディア向け報告会(午前11時半~午後1時)
昼から実施したメディア向け報告会では、まず国基研企画委員の岩田元陸上幕僚長が、昨年3月、米インド太平洋軍アキリーノ司令官が下院軍事委員会において、2027年に向けて中国の台湾侵攻準備が整えられるとの証言が紹介された。今回は、その侵攻準備状況の一端が見える中国軍の演習について中川研究員が説明する、との趣旨説明があり、報告会を開始した。
発表の後、出席記者からの質問に答える形で補足説明も行われ、活気ある議論が展開された。
【質疑応答】
Q:中国陸軍が実弾射撃演習を実施した多連装ロケットを防御する手段を台湾は持っているのか。
A:台湾は、多連装ロケットを迎撃する防空手段として天弓ミサイルシステムなどを所有する。しかし、一度に多くの弾数と波状攻撃があれば、守り切ることは困難だろう。台湾市民への心理的圧力としては十分過ぎるのではないか。
Q:今回の演習で、封鎖の対象が港に加えシーレーンに拡大されたが、これは今次演習で初めて登場したことか。
A:公開情報の上では、近年の演習の中で初めて確認された。封鎖の範囲を拡大することで、より一層台湾を孤立させる狙いがあると思われる。
Q:発表を聞くと中国軍の練度が上昇していることを痛感するが、次の段階はどういうことが予想されるか。
A:中国の訓練はこれから最盛期に向かい、冠演習を含めて各種訓練が繰り返されるものと予想する。特に訓練内容において、今まであまり表舞台に登場してこなかった武装警察の動きに注目したい。仮に中国軍が台湾に侵攻した場合、島内では武装警察が市民を統制することになるからである。加えて東部戦区では、実戦では不可欠な要素である補給や衛生を含めた統合訓練が実施されるか注目したい。
Q:すでにウクライナ戦争では無人機が多用されており、今後台湾事態においても無人機が活用されると考えるが、有効な対策はあるのか。
A:中国軍は実際に無人機を相当数保有している。日本周辺でも台湾東沖や南西諸島において、本年2月には6機の飛行を確認している。その都度領空侵犯への対処に向かう戦闘機の消耗は否めず、台湾では対応ラインを下げざるを得なくなっている。今後、スウォーム(群れ)攻撃の可能性を含め、高出力レーザー兵器や妨害電波など、早期に対策を確立する必要がある。
Q:尖閣諸島において海上民兵はどのように利用されるか。
A:海上民兵の利用法としては、大量の漁船に分乗した民兵が尖閣諸島の領海内で漁をする、漁民を装って上陸するなど、民兵か漁民かの区別が困難な状況を作り、日本政府の判断を遅らせることを企図するのではないか。時間の経過は速戦即決の中国軍を利することになるだろう。
この総合安全保障プロジェクト月次報告会は、記者向け報告会とともに、継続実施していく予定である。 (文責 国基研)






