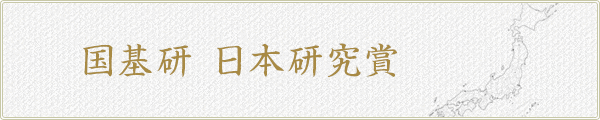
「国基研 日本研究賞」創設の趣旨
私たちは日本国の基本をゆるぎなく立て直し、本来の日本らしい姿を取り戻したいとの思いで2007年に国家基本問題研究所を創立した。日本独自の価値観を守りつつも、広く世界に視野を広げ、国際社会のよき一員でありたい。そのために、憲法、安全保障、教育など、日本が直面する国家的課題に果敢に取り組み、日本再生に貢献したいという切望が、私たちの原動力だった。
志を実現するには国際社会の日本理解を深め、諸国との相互尊重を確立することが欠かせない。だが、現実は私たちの願いから程遠く、多くの点で日本は誤解されている。とりわけ歴史問題に関する誤解は根深く、その誤解の壁は現在も私たちの前に立ちはだかる。日本と価値観を同じくする西側諸国でさえも、必ずしも、例外ではない。
誤解を解くのに一番よいのは、外国の人々に日本を知ってもらうことであり、なんとか日本研究の人材を育てたいと考えていたときに、寺田真理氏より御厚志をいただいた。志を同じくする氏の思いも反映して創設したのが日本研究賞である。
同賞に托す私たちの願いは、日本の姿、歴史、文化、文明、政治、戦争、価値観のすべてを、二十一世紀を担う国際社会の研究者に極めてもらうことだ。日本研究賞が自由かつ誠実な日本研究を進める一助となれば、それは私たちにとっての大いなる喜びである。
成功も失敗も含めて日本のありのままを研究してもらえれば、そこから生まれる評価は肯定的否定的とを問わず、自ずと偏見の壁を打ち破るはずだ。学問的誠実さに裏づけられた研究は、その全てが私たちにとっても貴重な学びとなるはずだ。
「国基研 日本研究賞」によって、日本の真の友人が国際社会にふえていくことを心から願っている。同時に、私は日本の文化文明、日本人の生き方を決定づける価値観は、必ず、二十一世紀の国際社会のより良い在り方に貢献できるものと、信じている。
国家基本問題研究所理事長 櫻井よしこ

日本研究賞を創設した意図と将来に向けてのビジョンについて、櫻井理事長と田久保副理事長が対談しました。
櫻井国家基本問題研究所の創設の趣旨はいくつかあったと思います。第一は戦後の日本のあり方を根本的に変えなければならない。そのためには、憲法改正が重要だということでした。もう一つは、それと同時進行で、海外における日本に対する、歪曲された理解、誤解を ... 続きを読む
要綱
- 一.
- 国家基本問題研究所は、政治、経済、安全保障、社会、歴史、文化の各分野で、日本に対する理解を増進する、内外の優れた日本関係研究を顕彰し、奨励する。
- 一.
- 原則として個人に対し、日本研究賞1点、1万ドルを受賞者に贈る。奨励賞は5千ドルとする。特別賞を出す場合もある。
- 一.
- 対象となるのは、近年刊行、発表された日本語か英語による作品で、日本に帰化した一世を含む外国人研究者とする。但し、特別賞の場合は、この限りではない。
- 一.
- 候補作品は、毎年末までに推薦委員その他識者に広く推薦を依頼、その結果を基に選考委員会が翌年春までに選考する。
- 一.
- 授賞式及びレセプションは、通常、毎年7月に行う。
第12回「国基研 日本研究賞」
受賞作品
| 日本研究特別賞 | ロビン・L・リエリー 米海軍史研究家
|
|---|
選考の経緯
第12回「国基研 日本研究特別賞」
ロビン・L・リエリー 米海軍史研究家
『日米史料による特攻作戦全史 航空・水上・水中の特攻隊記録』(小田部 哲哉編訳/並木書房、2024)
我々は、第二次世界大戦末期、戦況が不利の中、戦局打開を図つて日本軍が行つた一身を捨てて連合軍と戦つた「特攻隊」に特別の感慨を抱く。
戦ひにおける決死の攻撃は、第二次世界大戦の日本だけではなく古今東西、その例は少なくない。しかし、その規模と態様において、第二次世界大戦末期の日本の特攻作戦は、ほかにその例を見ないであらう。
「本書は1944年10月にフィリピンで始まり、1945年8月の日本の敗戦で終了した特攻隊で損害を受けた米艦艇の物語である」(訳者の前書)。アメリカ側が受けた特攻隊の全記録が、アメリカ側に残された資料を渉猟して詳細に記述されてゐる。したがつてアメリカ以外に行はれた特攻は記述されてゐない。
特攻隊は飛行機だけに限らない。潜航艇から人間魚雷など、攻撃を受けた艦船の記録が日付を追つて記述され、アメリカ軍が受けたものはほとんど全て網羅されてゐる。攻撃を受けた艦艇や近くの艦艇から撮影した写真など多数の写真も掲載されてゐる。また随所で被害を受けた艦艇の戦闘報告もはさまれてゐて臨場感がある。
たとへば、6機から8機の零戦が、空母マニラ・ベイを攻撃した際、「1機が直衛に撃墜された…。1機は豪海軍重巡洋艦…の艦中央部に体当たりした。1機は…のレーダー・アンテナに接触して横の海面に突っ込んだ。1機は…に達する前に被弾して、その横の海面に激突した。2機が本艦を攻撃し、1機目は砲弾を40発受けながらも飛行甲板まで達した。2機目は右舷の桁端にぶつかり右舷舷側から…の海面に突っ込んだ」(本書227頁)
特筆すべきは、訳者が、原著の記録を精査してそれに訳注を付してゐることである。たとへば、「4月13日、コノリイ(米艦艇の名)の上空に…九九式艦爆5機が現れた…。」の訳注では、「九九式艦爆は出撃していない。次の攻撃隊の機種を九九式艦爆に誤認している。第107振武隊(九七式戦)…」(本書349頁)
この訳注がほぼ全ページにわたつてゐるのである。また巻末には訳者による特攻隊一覧表などがつけられてゐる。単なる訳ではなくて「編訳」とした所以であらう。
本書の最後に著者は述べる。「この意味で、特別攻撃は米軍の猛威を止めることはできなかったが、成功したとみることができる。」(本書487頁)
もちろんこれは、特攻作戦を賛美したものではなく、事実の重みを粛然と受け止めた著者の感慨であらう。本書は、特攻といふ日本人の行動の記録集として当研究所の日本賞にふさはしいと考へる。
講評 選考委員 髙池勝彦
国基研副理事長・弁護士
選考委員
| 委員長 | 櫻井よしこ 国家基本問題研究所理事長 |
|---|---|
|
平川祐弘 東京大学名誉教授 渡辺利夫 拓殖大学顧問 髙池勝彦 国基研副理事長・弁護士 |
推薦委員
| 推薦委員 | ジョージ・アキタ 米ハワイ大学名誉教授 ブラーマ・チェラニー ケビン・ドーク ワシーリー・モロジャコフ ブランドン・パーマー 許世楷 アーサー・ウォルドロン エドワード・マークス デイヴィッド・ハンロン 楊海英 ロバート・D・エルドリッヂ ジューン・トーフル・ドレイヤー ロバート・モートン 蓑原俊洋 ペマ・ギャルポ 秦郁彦 李建志 ミンガド・ボラグ トシ・ヨシハラ 李宇衍 エヴァ・パワシュ=ルトコフスカ 李大根 ジェイソン・モーガン ジョン・マーク・ラムザイヤー 鄭大均 |
|---|






