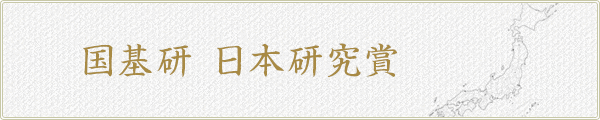
 2025年6月12日付産経新聞に、
第12回「国基研 日本研究賞」の
記事が掲載されました。
内容はPDFにてご覧いただけます。【 PDFを見る 】
2025年6月12日付産経新聞に、
第12回「国基研 日本研究賞」の
記事が掲載されました。
内容はPDFにてご覧いただけます。【 PDFを見る 】
日本研究特別賞
ロビン・L・リエリー (米海軍史研究家)
『日米史料による特攻作戦全史 航空・水上・水中の特攻隊記録』
(小田部 哲哉編訳/並木書房、2024)
受賞のことば

この本が日本で関心を呼んだのは、神風特攻隊に関する日本人が抱いていた疑問に答えたからだと考えています。日本軍は、部隊と航空機、そしてその攻撃目標については文書で記録を残しました。日本軍は、沖縄の米軍との戦闘に向かう航空機が出撃する前からその任務を知っていたが、特攻隊員の運命を知る術はありませんでした。特攻隊員は任務を遂行することが出来たのか、それとも出来なかったのか、この本は、この欠けている部分を埋めようとするものです。これはアメリカ人歴史家が日本軍の戦闘を評価したものであることをご了承願います。
「suicide:自殺」という言葉を「カミカゼ」攻撃で使うのは、主に西洋的な考えによるものです。現在の日本やアメリカの社会における「自殺」の一般的な用法は、うつ病や受け入れがたい生活状況の結果として、自らの手で命を絶つことです。「神風」とは、1281年に九州北部の博多湾でモンゴル艦隊を日本沿岸から追い払った台風のことです。これによりフビライ・カーンの脅威を終わらせ、モンゴルの支配から日本の独立を守ることが出来ました。
アメリカ人はどのようにして日本軍の戦闘行動についてこの言葉を使うようになったのでしょうか? 特別攻撃隊の本来の名称は「しんぷうとくべつこうげきたい」でした。傍受した日本軍の通信を翻訳する任務に就いていた日系アメリカ人が、「神風」という漢字を「カミカゼ」と読み間違えたことで、「カミカゼ」がアメリカ軍の間で使われるようになりました。
いわゆる 「特攻 」任務には、日本軍パイロットが連合軍の艦艇に航空機を体当たりさせるだけでなく、兵士自身、2種類の高速艇(陸軍のマルレ(連絡艇:㋹)と海軍の震洋)、そして桜花として知られる有人飛行爆弾によるものがありました。 震洋は爆薬を船首に搭載し、敵艦艇に体当たりさせて爆発させました。マルレの船尾には2つの爆雷が置かれ、マルレが敵艦艇の横で旋回する時に投下されるように設計されていました。当然のことながら、マルレの乗組員は爆雷の爆発から逃れることはできませんでした。
歩兵は戦車に対する刺突爆雷による自爆任務の訓練を受けることがありました。 これは、歩兵が戦車に駆け寄り、爆発物を付けた棒を戦車の側面に押し当てるものです。 この攻撃は、戦車を行動不能にするかもしれなせんが、歩兵が死ぬことは確実でした。同じ様な極端な例としては、地面に穴を掘り、その上を枝で覆ったものがあります。戦車がその上を通ると、中で潜んでいた歩兵が爆薬を持って立ち上がり、それを戦車の下で爆発させました。
桜花はロケット付きの有人飛行爆弾で、戦争末期に開発されました。 作戦に際し、桜花は爆撃機の下に搭載され、アメリカ艦艇の近くで放たれました。 桜花は滑空し、その後ロケットを点火して敵艦艇に突入しました。 これらの新兵器とこれを使いたいとの日本兵の思いが自国の防衛に際して「特攻」という考えにつながりました。
日本の若者たちは明治維新後何十年もの間、軍隊式の生活に従事するよう奨励されてきました。日本の学校制度は、1890年代から軍事訓練への傾斜を強め、日清戦争(1894年)と日露戦争(1904年)もこの動きを促進させました。学校の教育課程は、軍国主義と集団の結束力を育み、特に天皇と国家の結合に焦点を当てて天皇への崇敬を強調しました。この傾向は続き、1925年までには、日本軍将校が全国の中学校や高校で軍事科目を教えるようになりました。
やがて神風特攻隊員となった今村茂男の回想によれば、日本の小学校では早くも4年生から軍国主義的な道徳の授業が始まり、それが教育全般に亘ってきました。 彼が中学生になる頃には生徒はゲートルを巻き、指定された場所に集合してから行進して登校しなければなりませんでした。岡崎照幸は、福岡県直方市立鞍手中学校での日々をこう振り返っています。彼は1941年に10歳で入学しました。年長の生徒は14歳の時、特攻隊員訓練生の選抜試験を受けました。岡崎は立川キ-9機で離陸訓練を受けました。生徒たちは飛行機を急降下させる方法も学びましたが、着陸方法は教わりませんでした。 生徒たちの年齢が若かったため、特攻隊員の任務を受け入れることは簡単でした。彼らにとって特攻隊員は国に奉仕する輝かしいことに見えたのです。 今村も岡崎も、終戦のために訓練の成果を生かす機会がありませんでした。
従って、特別攻撃や「カミカゼ」という言葉は、日米で見方が異なります。日本では、若者たちは長年の洗脳教育によって、天皇は国家であり、その両方を守ることが自分たちの義務だと考えるようになったと理解されています。 アメリカ人の中には、特攻隊員の動機が理解できない者もいましたが、ほかの者は異なる見方をしています。 あるアメリカ海軍の元水兵はこう話しています:彼らは勇敢な兵士だった。
(訳者注:これはLCS(L)-61に乗艦されていたリエリー氏の父親が話されたこと。『日米史料による 特攻作戦全史 航空・水上・水中の特攻隊記録』 p. 48にも記載)
略歴
ロビン・リエリー氏は今までに海軍史と武道の歴史・練習方法に関する16冊の本と各種の記事を書いている。
リエリー氏は米国ニュージャージー州のライダー大学で政治学の学士号、同州のシートン・ホール大学で日本地域研究の修士号を取得。その後、同州のフリーホールド地域高校地区の歴史教師および学科監督として教育現場で32年間勤務して退職。その間、教鞭をとるかたわら、ニュージャージー州立ラトガース大学で学び、日本史の博士号取得のための授業と試験をすべて修了した。
同氏はニュージャージー州在住ですが、日本の歴史と文化に触れたのは10代後半だった。 1961年に米海兵隊に入隊した後、横浜近郊の厚木基地に1年半駐留した。 日本に到着すると、すぐに横浜で宏武館道場を見つけ、そこで長岡文雄師範から柔術と空手を組み合わせた神陰流柔術を学んだ。1963年に米国に戻ると、日本空手協会(JKA)の師範で、東京の拓殖大学を卒業後アメリカに渡り、ペンシルベニア州フィラデルフィアで空手を教えていた岡崎照幸師範と連絡を取った。氏は岡崎師範に長年師事、日本武道の上達に励んだ。 また、大学入学と同時に学費を工面するために空手を教え始め、60年以上空手の稽古と指導を続け、現在は八段。
横浜の道場で稽古をしていた時、親しくなった2人の日本人生徒から日本語と日本の家庭生活・習慣・考え方を教えてもらった。 また、ジャパンタイムズに掲載されていた、大学教授が大学生になる2人の子供たちのために英語の練習をしてくれるアメリカ人を探している、という広告に応じたことが幸いした。その家族はリエリー氏を多くの日本文化と触れることができる所へ連れて行くとともに、日本語の基礎を学ぶ機会を与えてくれた。 このような経験によって、氏は日本の歴史や文化に興味を持ち、学位の取得を目指すようになった。
同氏の最初の著書は1970年に出版された。 初期の著作は武道の歴史と練習方法を扱ったものだった。 1989年、父親の紹介で、第二次世界大戦中に太平洋戦域で大型上陸支援艇(LCS(L))に乗艦していたアメリカ海軍退役軍人の団体を知ることになった。その団体を通じて、父親が乗艦していた大型上陸支援艇(LCS(L)-61)の歴史の研究を始め、その後この戦域で戦ったすべての艦艇の行動を研究するようになった。氏の著書のうち5冊は、第二次世界大戦中の太平洋戦域におけるアメリカ海軍の行動を描いたものです。このうちの2冊は、Kamikazes, Corsairs and Picket Ships: Okinawa 1945『米軍から見た沖縄特攻作戦 カミカゼVS 米戦闘機、レーダー・ピケット艦』と、日本研究特別賞の対象となった本作品Kamikaze Attacks of World War II: A Complete History of Japanese Suicide Strike on American Ships, by Aircraft and Other Means 『日米史料による特攻作戦全史 航空・水上・水中の特攻隊記録』である。
武道関係の著書のいくつかはベトナム語、フランス語、ロシア語、ポルトガル語などほかの言語に翻訳されている。最新刊はRiver Warfare in Vietnam: A Social, Political, and Military History, 1945 to 1975, (McFarland Publishing (2014)です。
現在はヨーロッパの騎士道と日本の武士道を比較した新刊を執筆中。






